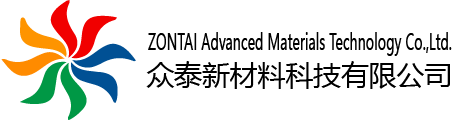構造用エポキシ樹脂の難燃特性を変更するにはどうすればよいですか?
エポキシ樹脂に難燃剤を多量に使用すると、材料の機械的特性に影響を与える可能性があり、硬化中や使用中に難燃剤が移行することで難燃効果が徐々に低下し、不安定なくすぶり状態になることがあります。
したがって、エポキシ樹脂の製造原理としては、反応性モノマーやくすぶり効果のある硬化剤を使用することが考えられます。カチオン性難燃剤がエポキシ樹脂の分子構造に導入されるため、最終的なエポキシ樹脂の耐久性が向上します。-くすぶり特性が安定して持続し、樹脂本来の機械的特性を維持できます。ガラス転移温度、機械的特性ペン、分子構造内に一定量のハロゲン、シリコン、耐衝撃性改良剤を含む機能性モノマーを追加することも、反応性モノマーおよび硬化剤と見なすことができます。
(1) 難燃性機能性モノマー原料
くすぶり機能を有するモノマーから合成されたこのタイプの構造くすぶり型エポキシ樹脂は、乾燥分子構造中にハロゲン、ケイ素、リン元素を多量に含み、優れたくすぶり性能を発揮します。
エポキシ樹脂の反応原料として通常のビスフェノールAの代わりにテトラブロモビスフェノールAを使用すると、安定性が良く、難燃性の高い高分子量の臭素化エポキシ樹脂が得られます。
(2) 難燃性硬化剤
ジクロロマレイン酸無水物、テトラブロモ無水フタル酸、リン含有アミン、アミン含有酸、リン酸アミドペンなどの通常の硬化剤の分子構造にハロゲン、シリコン、リンなどの難燃元素を導入したり、直接合成したりすること。分子設計による新しい難燃剤の開発など、いずれも注目を集めている研究方向です。